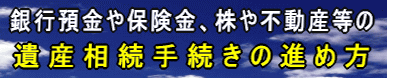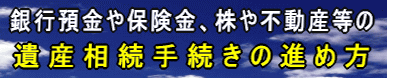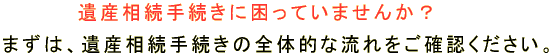|
|
�@ ���������葱�̎d�� ���������葱�̎d�� |
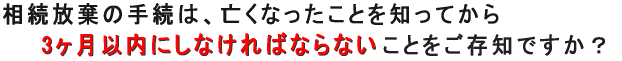
�� �S���Ȃ������̑������Y�ׂĂ݂āA�؋��Ȃǂ̃}�C�i�X���Y�̕��������ꍇ�A�R�����ȓ��ɑ��������̎葱�����Ă����Ȃ��ƁA�؋����܂߂����ׂẴ}�C�i�X���Y�𑊑����鎖�ɂȂ�܂��B
|
�����ŁA���̗l�ȏꍇ�A�S���Ȃ������̎؋��Ȃǂ������p���Ȃ����߂ɁA�����̊J�n��m������ �i���͖S���Ȃ�������m�������j ����R�����ȓ��ɁA�ƒ�ٔ��������������̐\�q���ƁA �S���Ȃ������Ƒ����l�̌ːЗ� ���o���܂��B
�����P�ɁA�w ���́A�����������܂��B�x �Ɛ錾���邾���ł́A�؋��Ȃǂ̎�藧�Ă���܂ʂ���鎖�͂ł��܂���B |
���ӓ_�F���Ȃ����������������̎葱�����Ă��A���ɑ����l������A���̕��B���؋��Ȃǃ}�C�i�X���Y�������肷�鎖�ɂȂ�܂��B
�ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA�Ⴆ�A�S���Ȃ������̎q���Ƃ��āA���Ȃ��Ƒ��ɂ��Q�l�����ꍇ�A���Ȃ������������̎葱��������ƁA���Ȃ��̑������� �i�S���Ȃ������̎؋��Ȃǃ}�C�i�X���Y���܂߂āj �����̂Q�l�ɔz������ĉ��Z������̂ł��B
�܂�A���Ȃ������������葱������ƁA�@�I�ɁA���Ȃ��͏��߂��瑊���l�ł͂Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B
����ɁA���ӂ��ׂ����Ƃ́A�S���Ȃ������̎q���S�������������葱�����ς܂��ƁA���ɑ�ʂł���S���Ȃ������̂����e����т��c���ꂪ�����l�ƂȂ�܂��B
�S���Ȃ������̂����e����т��c��������łɖS���Ȃ��Ă���ꍇ�A�܂��͑�S�������������葱�����ς܂��ƁA���ɑ�O���ʂł���S���Ȃ������̂��Z��o���̕��B�������l�ƂȂ�A�؋��������肷�邱�ƂɂȂ�܂��B
��O���ʂł���S���Ȃ������̂��Z��o���̕��B�S�������������葱�����ς܂����i�K�ŁA��ꏇ�ʎq���`��ʂ����e���c����`��O���ʂ��Z��o���ւ̑����͊��S�Ɏ~�܂�܂��̂ŁA�S�����S�ƂȂ�܂��B�������A�S���Ȃ������ɍȂ��������Ă���ꍇ�́A�Ȃ̂ݑ����l�ƂȂ�܂��̂ŁA�Ȃ����������葱�����ς܂��ƁA�����l�͂��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
��ꏇ�ʂȂǂ悭�킩��Ȃ����́A�����l�͈̔��̃y�[�W�����m�F���������B
|
�S���Ȃ������̎c�����������Y���A�؋��Ȃǃ}�C�i�X���Y�̕��������Ƃ킩���Ă���Ȃ�A�����l�S�� �i��ꏇ�ʁ`��O���ʂ܂Łj �ő��������葱�������Ă������Ƃ��A���������l���m �i�Z��o����e�ʊԁj �̃g���u������f�h�~�̂��߂ɂ���ԗǂ����@�ł��傤�B
���T�C�g�� �w�S���Ή��I��Y�����葱���ɕK�v�Ȃ��ׂĂ̌ːГ��{���̃��N���N����s �x�́A�����葱���̂P�ł��鑊�������葱���ɂ��S���Ή����Ă���܂��̂ŁA��ꏇ�ʂ̒i�K�ŁA���̂܂܌ːЗނ��o���Ă����������OK�ƂȂ��Ă���܂��B���Ђ����p���������B
���T�C�g�̑�s�́A���ꂼ��̒i�K���i��ꏇ�ʁ`��O���ʁj�̑�s�ƂȂ��Ă���܂��B�܂�A��ꏇ�ʂ���̑������������\��̏ꍇ�A��ꏇ�ʂ̎��Ƒ�ʂ̎��A��O���ʂ̎��ɂ��ꂼ���{�����{�����l�̐��ɂ����Z�����{�������K�v�ƂȂ�܂��B�������A��ʂ��S���S���Ȃ��Ă��鎞�́A��ʂ̊�{�����̓T�[�r�X�v���܂��B
�Ƃ����̂��A�܂��́A��ꏇ�ʑS�������������葱�����������Ȃ��ƁA���̑�ʂ̑��������葱�����ł��Ȃ�����ł��B�܂�A��ꏇ�ʂ����O���ʂ܂ł̑����������ɍs�����Ƃ͂ł��Ȃ�����ł��B�ƒ�ٔ������t���Ă���܂���B
�܂��A���ꂼ��̏��ʂɂ�����K�v�ȌːЗނ��قȂ�܂��̂ŁA���ꂼ��̏��ʂ̑����������ςi�K�łȂ��ƌːЗނ���������擾���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂����Ԃ�����ł��B
��ꏇ�ʂ����O���ʂ̑������������\��̏ꍇ�A���\���ݎ��Ƀ��b�Z�[�W�Ƃ��Ă��L�������������A���₢���킹���������܂�����A������ŏڂ�������ƑΉ���v���܂��B���ꂼ��̑��������������͌����Ă��܂��̂ŁA���}������������Ǝv���܂��B
���͂Ƃ�����A�܂��͑�ꏇ�ʂ̑����������ł������}���ōs�����Ƃ��挈�ł��B
�� ���������̎葱���̗���
�@ �����̊J�n �i�l���S���Ȃ������A�܂��͖S���Ȃ������Ƃ�m�������j
�A �S���Ȃ������̎c�����������Y���A�؋��Ȃǃ}�C�i�X���Y�̕��������A���������̎葱�������邱�Ƃ����߂�B
| ���������葱���ɂ́A�S���Ȃ������Ƒ����l�̌ːЗނ��K�v�Ƃ���Ă��܂��̂ŁA�ł��邾�������ːЗނ̎����s���������ǂ��ł��傤�B�ːЗނ̎��ɂ́A�f�l���s���ƁA�ӊO�Ǝ��Ԃ���������̂ł��B���������̎葱���́A�����̊J�n �i�l���S���Ȃ������A�܂��͖S���Ȃ������Ƃ�m�������j����R�����ȓ��ɂ��Ȃ��ƁA�Ȍ㑊���������ł��Ȃ��Ȃ邩��ł��B |
|
�B �S���Ȃ������̍Ō�̏Z���n�̉ƒ�ٔ����ɁA���������\�q���ƁA�S���Ȃ������Ƒ����l�̌ːЗނ��o���܂��B
�E ��o������͒N�ł��ǂ��̂ł����A�{�l�ȊO�̕�����o����ꍇ�́A���L�C�ɂ���Ė{�l�m�F���s���܂��B
�E �{�l����o����ꍇ�́A���̏�ʼn^�]�Ƌ��ȂǂŖ{�l�m�F���s���A���L�C���ȗ����邱�Ƃ������܂��B |
|
�C �ƒ�ٔ������A�\�q�҂̏Z���֏Ɖ�Ɖ��𑗂��Ă��܂��̂ŁA�����ƒ�ٔ����ɑ���Ԃ��܂��B
�D ���������̎ʒm�������A���������葱���͊����ł��B
| �����A���҂ȂǂɁA�ؖ������ق����ƌ���ꂽ��A�ƒ�ٔ����ɏؖ����̔��s�𐿋��ł��܂��B |
|
�� ���������̐\�q�̎d��
|
�\�q��́A�푊���l�i���S���Ȃ������j�̍Ō�̏Z���n�̉ƒ�ٔ����ł��B
�\�q�l�Ƃ��ẮA�ʏ�A�����l�ł��B
�������A�����l�̂P�l�ɖ����N�Җ��͐��N��㌩�l������ꍇ�ɂ́A���̖@��㗝�l�i�e�Ȃǁj���㗝���Đ\�q���鎖�ɂȂ�܂��B�܂��A�����N�� �� ���̖@��㗝�l �i�e�Ȃǁj ���A�����S���Ȃ������̑����l�ł����āA�����N�҂݂̂������̕�����\�q���鎞�����ʑ㗝�l�̑I�C���K�v�ƂȂ�܂��B���ʑ㗝�l�Ƃ��ẮA�f���i�����j���f��i����j����ɂȂ��Ă��������Ƃ悢�ł��傤�B���ʑ㗝�l�̑I�C�͂��������ƒ�ٔ����ɒ�o���邱�ƂɂȂ�܂��B
�\�q���ԂƂ��ẮA���Ȃׂ̈ɑ����̊J�n�����������Ƃ�m�����Ƃ�����R�����ȓ��ƂȂ��Ă���܂��̂ł����Ӊ������B
|
�\�q�ɕK�v�ȏ��ނƂ��ẮA
�@�@�@ |
�E ���������̐\�q���@�@1��
�E ��������������\�q�l �i�ʏ�A�����l�j �̌ːГ��{�@�@1��
�E �푊���l �i���S���Ȃ������j �̏��Г��{���͌ːГ��{�Ɓ@�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z���[�̏��[�܂��͌ːЂ̕��[�@�@�e1��
�@�i���P�[�X�ɂ��A���̑��̎��������߂���ꍇ������܂��B�j |
|
|